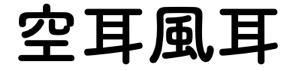みんなしばらく子育て時期は遠ざかっていたが、また気分転換が欲しい年になった。
今年は特に春を待っていた。なぜか浄瑠璃寺の馬酔木の頃には行ったことがなかった。浄瑠璃寺は秋でしょうと周りがいうので、私も秋にはたびたび訪れ、春の機会を逃していたが、道路が整備されたので時間もかからずいけるようになった。
平安、鎌倉の時代から戦火を逃れてきた建物は市街から随分離れた所にあってひっそりと寂れて古びているが、長い歴史を思うと遠くて近い人の営みの祈りや願いが今でも感じられる。
私は神も仏も実感できてはいないし、祈りは心に向かって唱えるのだとか理屈を並べて、縁なき衆生に近いけれど、古い裳階の形や屋根の優美な曲線や、並んでいる仏様の顔を見ると何か畏れのような気持が湧いてくる。
こうして庶民の願いや希望や歓びや嘆きの声を聴きながら仏たちは祈りの声を静かにそっとあずかってきたのかと思うと、長い歴史の中の庶民の暮らしの重みを感じる。
人はそれぞれ違った心の形を自分の中に持っている、疲れた時は、やはりここで祈って、荷物を預けて帰るのだろうか。
この春、僕はまえから一種の憧れをもっていた馬酔木(あしび)の花を大和路のいたるところで見ることができた。
そのなかでも一番印象ぶかかったのは、奈良へ著(つ)いたすぐそのあくる朝、途中の山道に咲いていた蒲公英(たんぽぽ)や薺(なずな)のような花にもひとりでに目がとまって、なんとなく懐かしいような旅びとらしい気分で、二時間あまりも歩きつづけたのち、漸(や)っとたどりついた浄瑠璃寺の小さな門のかたわらに、丁度いまをさかりと咲いていた一本の馬酔木をふと見いだしたときだった。
いつ来ても参道の入り口にお土産の店があり、雑器や秘仏のレプリカや自家製の梅干しや漬物を売っている。
記念に小さな陶器の置物を買って帰る。
傍らに花さいている馬酔木(あしび)よりも低いくらいの門、誰のしわざか仏たちのまえに供えてあった椿の花、堂裏の七本の大きな柿の木、秋になってその柿をハイキングの人々に売るのをいかにも愉(たの)しいことのようにしている寺の娘、どこからかときどき啼(な)きごえの聞えてくる七面鳥、――そういう此のあたりすべてのものが、かつての寺だったそのおおかたが既に廃滅してわずかに残っているきりの二三の古い堂塔をとりかこみながら――というよりも、それらの古代のモニュメントをもその生活の一片であるかのようにさりげなく取り入れながら、――其処にいかにも平和な、いかにも山間の春らしい、しかもその何処かにすこしく悲愴(ひそう)な懐古的気分を漂わせている。
自然を超えんとして人間の意志したすべてのものが、長い歳月の間にほとんど廃亡に帰して、いまはそのわずかに残っているものも、そのもとの自然のうちに、そのものの一部に過ぎないかのように、融(と)け込(こ)んでしまうようになる。そうして其処にその二つのものが一つになって――いわば、第二の自然が発生する。そういうところにすべての廃墟の云いしれぬ魅力があるのではないか? ――そういうパセティックな考えすらも(それはたぶんジムメルあたりの考えであったろう)、いまの自分にはなんとなく快い、なごやかな感じで同意せられる。……
また「風立ちぬ」の名文を読んで見よう。文章の書き方が少しは上達するかもしれない。